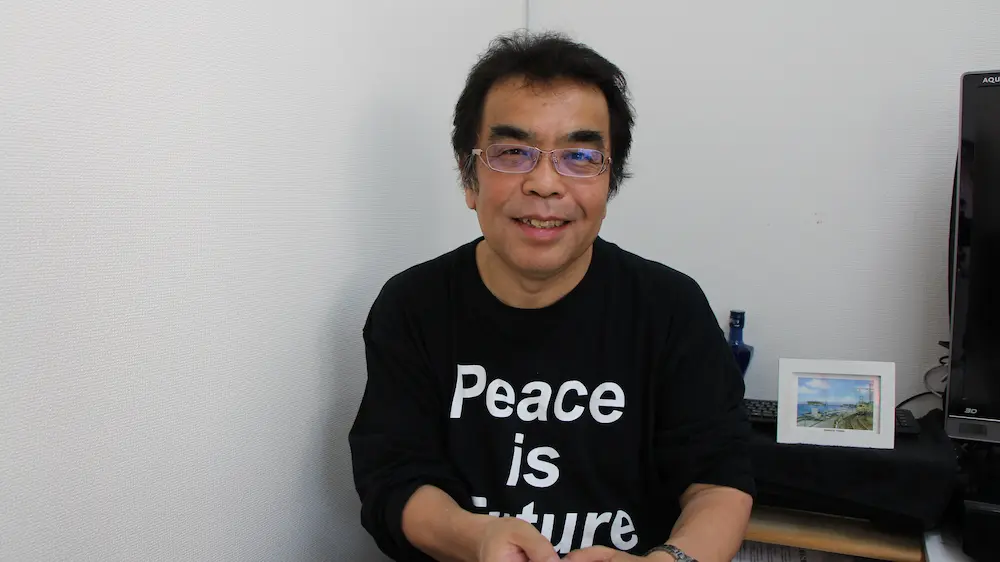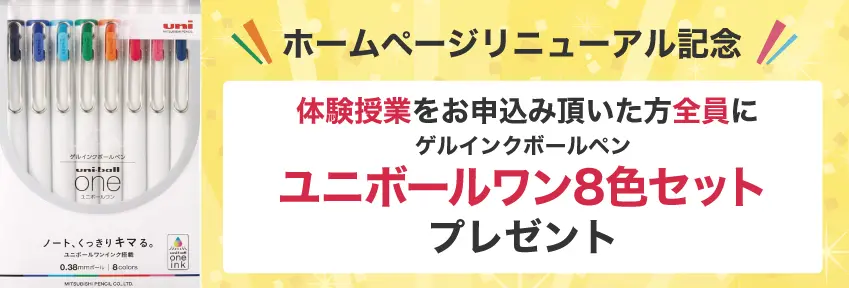1. 令和8年度入試の概要と予想日程
神奈川県公立高校入試は、県内全公立高校(全日制、定時制、通信制)で実施される「共通選抜」を基本としています。令和7年度の日程を参考に、令和8年度の主な日程を以下のように予想します(正式発表は2025年5月上旬予定):
- 出願期間:2026年1月下旬~2月初旬(例:1月27日~1月30日)
- 志願変更期間:2026年2月初旬(例:2月3日~2月5日)
- 学力検査:2026年2月中旬(例:2月13日)
- 特色検査・面接:2026年2月中旬(例:2月13日、16日、17日)
- 合格発表:2026年2月末(例:2月27日)
- 二次募集:出願は3月初旬、検査は3月中旬、合格発表は3月中旬
全日制の学力検査は、国語、数学、英語、理科、社会の5教科で各50分、100点満点です。定時制では英語、国語、数学の3教科が基本で、特色検査を実施する学校では教科数が3~4教科に減ることがあります。
2. 選抜制度の特徴と予想される変更点
2.1 共通選抜と2段階選抜
神奈川県の入試は、共通選抜を通じて1回のみ実施され、合否判定は第1次選考(募集定員の90%)と第2次選考(残り10%)の2段階で行われます。第1次選考では、調査書(内申点)、学力検査、特色検査(実施校のみ)が評価され、第2次選考では調査書の「主体的に学習に取り組む態度」の評価が加わります。令和6年度から面接が共通選抜から廃止され、特色検査の一環として実施されるようになったため、この制度は令和8年度も継続すると予想されます。
2.2 内申点の計算
内申点は、中学2年生(45点満点)と中学3年生(90点満点、評定2倍)の9教科の評定を合計し、135点満点を100点に換算します。一部の学校では、特定の教科(最大3教科)を1~2倍に重点化する傾斜配点が採用されます。令和8年度でもこの計算方法は変更されない見込みですが、志望校ごとの配点比率や重点化教科の確認が重要です。
2.3 特色検査
特色検査は、自己表現検査、実技検査、面接の3種類で、学力向上進学重点校(横浜翠嵐、湘南、厚木、柏陽)とエントリー校(計18校)では共通問題・共通選択問題が使用されます。自己表現検査では、論理的思考力や表現力を測る記述問題や集団討論が課され、例えば「社会問題に対する自分の意見」を600~800字で記述する形式が想定されます。実技検査は、美術、音楽、スポーツなどの専門学科で実施されます。令和8年度の特色検査実施校や概要は、2025年6月中旬に発表予定です。
2.4 学力検査の傾向
学力検査は、思考力、判断力、表現力を重視する問題が特徴で、難度が高い傾向にあります。英語は長文読解やグラフ読み取り、数学は図形証明や応用問題、理科は実験データ分析、国語は複数資料の読み取り、社会は歴史・公民の融合問題が頻出です。令和7年度では社会がやや易化、英語が難化傾向だったため、令和8年度も教科ごとの難易度変動に注意が必要です。
3. 受験動向と倍率
3.1 募集定員と志願者数
令和7年度の全日制募集定員は40,058人で、前年比550人減でした。令和8年度も少子化や学校再編により、募集定員の微減が予想されます。公立中学校卒業予定者数は66,000人前後で推移し、志願者数は約46,000人、平均競争率は1.17倍程度と、全体的な競争は緩やかな状態が続く見込みです。ただし、横浜翠嵐(倍率1.5~2.0倍)や湘南などの進学重点校は高倍率が予想されます。
3.2 私立志向の影響
私立高校への志望者が増加傾向にあり、令和7年度では公立志願者が前年比で減少しました。この背景には、私立の学費補助制度や大学入試への対応力向上があります。令和8年度もこの傾向が続き、公立と私立の併願戦略が受験生にとって重要となるでしょう。

3.3 学校再編・統合
令和7年度で横浜旭陵、永谷、深沢が募集停止、二俣川看護福祉高校が普通科に改編されました。令和8年度以降も、臨海セミナーによると一部高校で統廃合や学科改編が予定されており、志望校選択に影響を与える可能性があります。受験生は、2025年夏以降の県教育委員会の発表を確認する必要があります。
4. 受験対策のポイント
4.1 学力検査対策
- 英語:長文読解のスピード強化と「絵のストーリー説明」問題対策。過去問で時間配分を練習し、文法と表現力を磨く。
- 数学:図形証明や応用問題に対応し、選択式問題の解法パターンを習得。低正答率問題(例:令和7年度数学問3(ウ)、正答率3.4%)に慣れる。
- 国語:複数資料の読み取りや心情把握の記述問題対策。9分以内に長文を読み解くコツを身につける。
- 理科・社会:実験問題(例:電解質の水溶液)や歴史・公民の融合問題を重点的に学習。基礎知識の定着が鍵。
4.2 内申点対策
中学3年生の評定が2倍で計算されるため、定期テストや授業態度を重視。「主体的に学習に取り組む態度」(A:3点、B:2点、C:1点)の評価が第2次選考で影響するので、積極的な学習姿勢を示すことが重要です。
4.3 特色検査対策
進学重点校を目指す場合、共通問題・共通選択問題の過去問を活用し、論理的思考や記述力を強化。集団討論や作文では、具体例を交えた説得力のある表現を練習。実技検査は、志望校の要求する技能(デッサン、スポーツ、楽器など)を早めに準備。
4.4 志願変更の戦略
志願変更期間(2月初旬)に倍率情報を確認し、保護者や塾と相談して戦略を立てる。11月下旬の進路希望調査を参考に、志望校の人気動向を把握。倍率に一喜一憂せず、模試結果を基に冷静な判断を。
5. 今後の展望
5.1 教育改革の深化
新学習指導要領に基づく「学びに向かう力」の評価が、特色検査や内申点で一層重視される見込みです。思考力・表現力を問う問題が増加し、暗記型学習では対応が難しくなるため、受験生は自分で考え、表現する習慣を早めに身につける必要があります。
5.2 デジタル化の進展
令和6年度から導入されたインターネット出願は、令和8年度も継続され、受検票印刷や合格発表もオンラインで行われます。今後、オンライン面接やAIを活用した評価の導入が検討される可能性があり、受験生はデジタルリテラシーの向上も求められるでしょう。
5.3 地域格差と進学機会
募集定員の削減や学校再編により、郊外エリアでの進学機会が制限される懸念があります。進学重点校が横浜・川崎に集中する中、県教育委員会はインクルーシブ教育や追検査の拡充を通じて、多様な受験生への対応を強化する方針です。
6. まとめ
令和8年度神奈川県公立高校入試は、共通選抜の1回実施、2段階選抜、特色検査の多様化が特徴です。募集定員の微減や私立志向の高まりを背景に、戦略的な志望校選択が求められます。学力検査の難度の高さや内申点の重要性を踏まえ、早めの対策が成功の鍵です。特に進学重点校を目指す受験生は、特色検査への準備が不可欠です。教育改革やデジタル化の進展を見据え、柔軟な学習姿勢で臨むことが、受験生にとって最適な道となるでしょう。
参考文献: