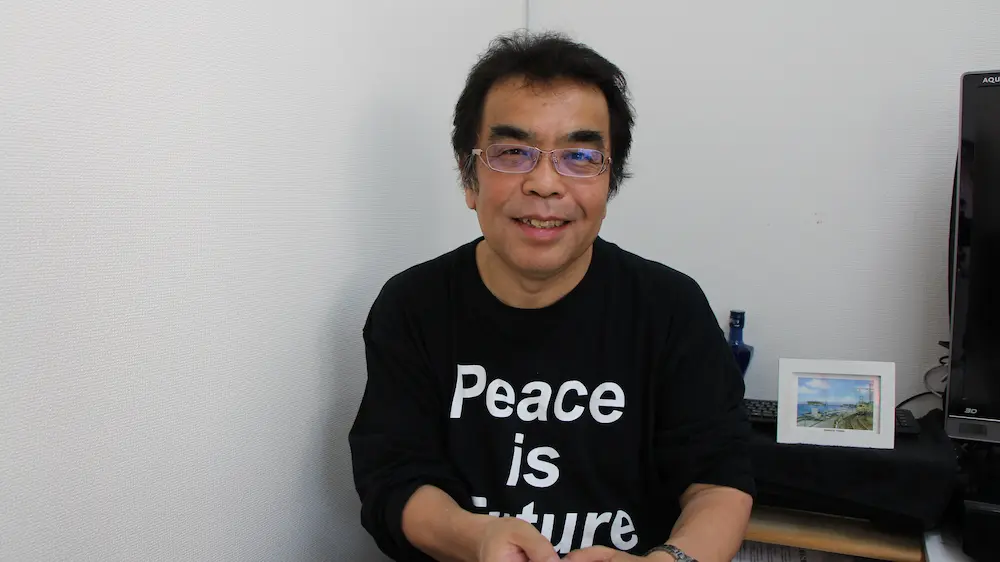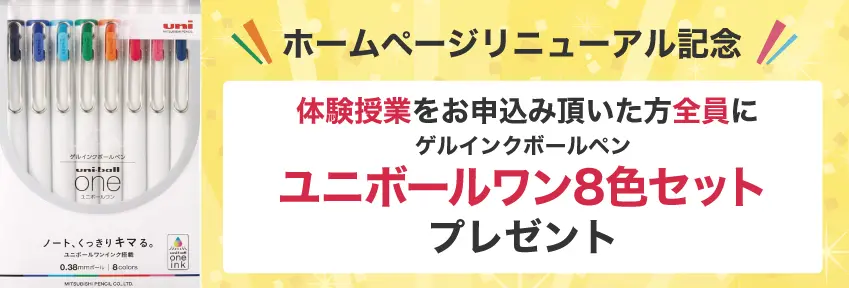「勉強の基本は詰め込みです。」
この言葉に違和感を覚える方もいるかもしれません。現代教育では「探求型学習」や「アクティブラーニング」がもてはやされ、「詰め込みは古い、非効率な学習法]と見なされがちです。しかし、私はKOSHIN学院の塾長として、そして30年以上教育の現場に立ち続けてきた者として、あえてこの言葉を強く主張したいと思います。
なぜなら、思考力とは空中に浮かぶものではなく、確かな知識の土台の上に築かれるものだからです。
【動画】教育の原点は詰め込み教育
基礎知識がなければ「探求」できない
「探求型学習」とは、子どもたちが自ら問いを立て、調べ、考え、議論し、答えを導き出す学習スタイルです。確かに魅力的ですし、将来的には必要な力です。しかし、問いを立てるには、まず「何を問うべきか」がわかっていなければなりません。そしてそれは、基礎的な知識があってこそ可能になります。
例えば、分数の計算ができない生徒に「この割合は適切か?」と問うても、意味がありません。割り算の概念が理解できていなければ、割合の妥当性を判断することはできないのです。思考力とは、知識を材料として使う力です。材料がなければ、料理はできません。
<参照:LINK>
「学力低下」の原因はスマホでもコロナ禍でもない?法学者も指摘「小学校での探究やグループワークの増加」が問題か
最難関校が「探求」を謳わない理由
興味深いことに、最難関とされる中学・高校の入試問題には、「探求型」や「グループ学習」的な要素はほとんど見られません。彼らが求めているのは、まず「基礎的な知識と論理的な思考力」です。つまり、学校側は「探求」は入学後に自ら行うものであり、入学前にはまず土台となる知識をしっかりと身につけてほしいと考えているのです。
これは、教育の本質をよく理解している証拠です。知識がなければ、思考は空回りします。グループで議論しても、誰も正しい情報を持っていなければ、議論は感情論に終始するでしょう。
小中学生に必要なのは「知識の蓄積」
小中学生の段階では、まず「詰め込み」によって基礎的な知識を身につけることが最優先です。漢字、語彙、計算、歴史の年号、理科の基本法則──これらはすべて、将来の思考力や探求力を支える「道具」です。道具がなければ、どんなに創造力があっても形にすることはできません。
もちろん、ただ暗記するだけでは意味がありません。KOSHIN学院では、詰め込みを「理解を伴った蓄積」と定義しています。意味を理解し、繰り返し使い、定着させる。そうして初めて、知識は「使える道具」として機能します。
自ら学ぶ力は、土台があってこそ育つ
「自ら学ぶ力」を育てたい──これはすべての教育者の願いです。しかし、自ら学ぶには「何を学ぶべきか」「どう学べばよいか」がわかっていなければなりません。その判断力もまた、基礎知識の上に築かれるものです。
KOSHIN学院では、まず知識の土台を築き、その上に「考える力」「自ら学ぶ力」を育てていきます。これは、農業に例えるなら「耕す」こと。土を耕し、種を蒔き、水を与え、太陽の光を浴びせる──そのすべてが揃って初めて、芽は出るのです。
小中学生は、まず基礎を作ることが先!
それでは今日はこの辺で! また明日♪
【KOSHIN学院は神奈川県平塚市田村にある、一生懸命頑張る生徒をトコトン応援する高校受験専門の学習塾です!】
しつこい勧誘は絶対にイタシマセンので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください♪